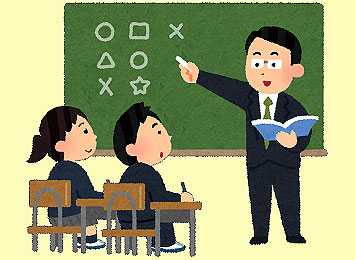「地方鉄道法」(ちほうてつどうほう)は、地方公共団体又は私人が一般公衆の利用のために、運輸大臣の免許を受けて敷設する地方鉄道(軌道を除く)の敷設・運営について規定した法律でした。「私設鉄道法」(明治33年法律第64号)と「軽便鉄道法」(明治43年法律第57号)を廃止し、再構成して制定されたのです。
全45条からなり、前身法同様、その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していましたが、軌道と異なり、特別の場合を除き道路上に敷設することはできませんでした。本法が適用される鉄道事業者を「地方鉄道会社」と呼称し、その鉄道路線は、「地方鉄道線」あるいは「地方鉄道」と呼ばれることとなります。
しかし、日本国有鉄道の分割民営化に伴い、当法が前提とする鉄道の「国有」と「民営」の枠組みがなくなることから、廃止・代替されて、1986年(昭和61)12月5日に「鉄道事業法」が公布されました。
以下に、「地方鉄道法」(大正8年法律第52号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
全45条からなり、前身法同様、その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していましたが、軌道と異なり、特別の場合を除き道路上に敷設することはできませんでした。本法が適用される鉄道事業者を「地方鉄道会社」と呼称し、その鉄道路線は、「地方鉄道線」あるいは「地方鉄道」と呼ばれることとなります。
しかし、日本国有鉄道の分割民営化に伴い、当法が前提とする鉄道の「国有」と「民営」の枠組みがなくなることから、廃止・代替されて、1986年(昭和61)12月5日に「鉄道事業法」が公布されました。
以下に、「地方鉄道法」(大正8年法律第52号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「地方鉄道法」(大正8年法律第52号)1919年(大正8)4月10日公布、同年8月15日施行
第一条 本法ハ軌道条例ニ規定スルモノヲ除クノ外道府県其ノ他ノ公共団体又ハ私人カ公衆ノ用ニ供スル為敷設スル地方鉄道ニ之ヲ適用ス
地方鉄道業者カ運送営業ノ為支線ヲ敷設スルトキハ公衆ノ用ニ供セサル場合ト雖本法ヲ適用ス
道府県其ノ他ノ公共団体又ハ私人カ専用ニ供スル為敷設スル鉄道ニシテ政府ノ鉄道又ハ地方鉄道ニ接続スルモノニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 地方鉄道ハ人力又ハ馬力其ノ他之ニ類スルモノヲ以テ動力ト為スコトヲ得ス
第三条 地方鉄道ノ軌間ハ三呎六吋トス特別ノ場合ニ在リテハ四呎八吋半又ハ二呎六吋ト為スコトヲ得
第四条 地方鉄道ハ之ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第五条 地方鉄道会社ノ株金ノ第一回払込金額ハ株金ノ十分ノ一迄下ルコトヲ得但シ兼業トシテ地方鉄道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第六条 地方鉄道会社ハ株金全額払込前ト雖監督官庁ノ認可ヲ受ケ線路ノ延長又ハ改良ノ費用ニ充ツル為其ノ資本ヲ増加スルコトヲ得但シ軌道会社ニ非サル会社カ兼業トシテ地方鉄道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七条 地方鉄道会社ハ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ社債ヲ募集スルコトヲ得ス
社債ハ総株金四分ノ一以上ノ払込アリタル後ニ非サレハ之ヲ募集スルコトヲ得ス
社債ノ額ハ鉄道抵当法ニ依ル債務ノ額ト併セテ総株金払込額ヲ超ユルコトヲ得ス但シ旧債償還ノ為ニスル場合ニ於テハ旧債務ノ額ハ之ヲ算入セス
第八条 鉄道及其ノ附属物件ハ鉄道抵当法ニ依ルニ非サレハ之ヲ担保ト為スコトヲ得ス
鉄道ノ附属物件ハ命令ノ定ムル所ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ貸渡又ハ讓渡スルコトヲ得ス
第九条 地方鉄道会社ハ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ他ノ事業ヲ営ムコトヲ得ス
第十条 地方鉄道会社ハ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併ヲ為スコトヲ得ス
合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立シタル会社ハ合併ニ因リテ消滅シタル会社ノ免許ニ属スル権利義務ヲ承継ス
第十一条 免許、許可又ハ認可ニハ条件ヲ附スルコトヲ得
第十二条 地方鉄道業ヲ営マムトスル者ハ左ノ書類及図面ヲ提出シ主務大臣ノ免許ヲ受クヘシ
一 起業目論見書
二 線路予測図
三 建設費概算書
四 運送営業上ノ收支概算書
免許ニハ工事施行ノ認可ヲ申請スヘキ期限ヲ附ス
第十三条 免許ヲ受ケタル者ハ左ノ書類及図面ヲ監督官庁ニ提出シ工事施行ノ認可ヲ受クヘシ
一 線路實測図
二 工事方法書
三 建設費予算書
四 免許ヲ受ケタル者カ会社ノ発起人ナルトキハ定款及会社ノ設立登記謄本
工事施行ノ認可ニハ工事ノ着手及竣功ノ期限ヲ附ス
第十四条 地方鉄道業者ハ天災事変其ノ他已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ第十二条第二項又ハ前条第二項ノ規定ニ依リテ附セラレタル期限ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得
第十五条 左ニ掲クル土地ヲ以テ鉄道用地トス
一 線路用地
二 停車場、信号所、車庫及貨物庫等ノ建設ニ要スル土地
三 鉄道専用ニ供スル発電所、変電所及配電所等ノ建設ニ要スル土地
四 鉄道構內ニ職務上常住ヲ要スル鉄道係員ノ舍宅及運輸保線ノ職務ニ從事スル鉄道係員ノ駐在所等ノ建設ニ要スル土地
五 鉄道ニ要スル車両、器具、機械ヲ修理製作スル工場及其ノ資材、器具、機械ヲ貯藏スル倉庫等ノ建設ニ要スル土地
第十六条 道路、橋梁、河川、運河及溝渠等ニ関スル工事ノ施設ハ所管行政庁ノ許可ヲ受クヘシ
第十七条 政府又ハ政府ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ地方鉄道ニ接続シ若ハ之ヲ横断シテ鉄道若ハ軌道ヲ敷設シ又ハ地方鉄道ニ接近シ若ハ之ヲ横断シテ道路、橋梁、河川、運河及溝渠等ヲ造設スルトキハ地方鉄道業者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
前項ノ場合ニ於テ公益上必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ地方鉄道業者ニ設備ノ共用又ハ変更ヲ命スルコトヲ得
設備ノ共用又ハ変更ニ要スル費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第十八条 地方鉄道業者ハ監督官庁ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ免許ニ屬スル権利義務ヲ他人ニ讓渡スルコトヲ得
第十九条 左ノ場合ニ於テハ免許ハ其ノ效力ヲ失フ
一 工事施行ノ認可ヲ申請スヘキ期限迄ニ認可ヲ申請セサルトキ
二 工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ
三 工事施行ノ認可ニ附シタル工事著手ノ期限迄ニ工事ニ着手セサルトキ
四 営業廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ
免許ヲ受ケタル者死亡シタルトキハ相続人ハ免許ニ属スル権利義務ヲ承継スルコトヲ得
第二十条 地方鉄道業者ハ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ運輸ヲ開始スルコトヲ得ス
第二十一条 地方鉄道業者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金ヲ定メ監督官庁ノ認可ヲ受クヘシ
監督官庁ハ公益上必要アリト認ムルトキハ運賃及料金ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第二十二条 地方鉄道業者ハ旅客列車及混合列車ノ発着時刻及度数ヲ定メ監督官庁ノ認可ヲ受クヘシ
監督官庁ハ公益上必要アリト認ムルトキハ列車ノ発着時刻及度数ノ変更ヲ命スルコトヲ得
第二十三条 監督官庁ハ監査員ヲ派遣シテ鉄道ノ工事、運輸保線ノ状態、会社及財産ノ実況ヲ監査セシムルコトヲ得
鉄道ノ工事、運輸保線ノ状態及会計ノ整理ニ付法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ違ヒ又ハ不適当ナリト認ムルモノアルトキハ監督官庁ハ其ノ改築又ハ改善ヲ命スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ其ノ工事、運輸又ハ設備使用ノ停止ヲ命スルコトヲ得
監査員ハ地方鉄道業者又ハ其ノ役員若ハ使用人ニ説明ヲ求メ金櫃、帳簿、書類及図面ヲ検閲スルコトヲ得
第二十四条 地方鉄道業者ハ地方鉄道ノ監督事務ニ関シ往復スル吏員ニシテ監督官庁ノ発行スル証票ヲ携帶スル者ヲ無賃ニテ乗車セシムヘシ
第二十五条 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他ノ鉄道又ハ軌道トノ連絡運輸又ハ直通運輸ヲ命スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ設備ノ共用又ハ変更、運輸ノ手続、運賃ノ割合及費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第二十六条 地方鉄道業者ハ監督官庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ鉄道ノ貸借又ハ営業若ハ運転シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス
第二十七条 地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス
地方鉄道会社ノ解散ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ效力ヲ生セス
第二十八条 主務大臣ハ地方鉄道ノ会計及運賃ノ割引ニ関シ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第二十九条 地方鉄道業者ハ法令ノ定ムル所ニ依リ平時及戦時ニ於テ鉄道ヲ軍用ニ供スル義務ヲ負フ
第三十条 政府カ公益上ノ必要ニ因リ地方鉄道ノ全部又ハ一部及其ノ附屬物件ヲ買收セムトスルトキハ地方鉄道業者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
地方鉄道ノ一部買收セラレタル為残存線路ノミニ付営業ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ地方鉄道業者ハ該線路及其ノ附屬物件ノ買收ヲ申請スルコトヲ得
第三十一条 買收価額ハ最近ノ営業年度末ヨリ遡リ既往三年間ニ於ケル建設費ニ対スル益金ノ平均割合ヲ買收ノ日ニ於ケル建設費ニ乘シタル額ヲ二十倍シタル金額トス
前項ノ益金トハ営業收入ヨリ営業費及賞与金ヲ控除シタルモノヲ謂ヒ益金ノ平均割合トハ三年間ニ於ケル毎営業年度末ノ開業線建設費ノ合計ヲ以テ同期間ニ於ケル益金ノ合計ヲ除シタルモノニ一年間ニ於ケル営業年度ノ数ヲ乗シタルモノヲ謂フ
営業收入及営業費ノ計算ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第三十二条 買收ノ日ニ於テ運輸開始後前条第一項ニ規定スル三年ヲ経過シタル線路ヲ有セサル場合又ハ前条第一項ノ金額カ建設費ニ達セサル場合ニ於テハ其ノ建設費以内ニ於テ協定シタル金額ヲ以テ買收価格トス
第三十三条 地方鉄道業者カ鉄道若ハ其ノ附屬物件ノ補修ヲ為サス又ハ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ依リ改築若ハ改造ヲ為スヘキ場合ニ於テ之ヲ為ササルトキハ補修ニ要スル金額ハ之ヲ営業費ニ加算シ改築又ハ改造ニ要スル金額ハ之ヲ買收価額ヨリ控除ス
第三十四条 買收ヲ受クヘキ地方鉄道業者カ兼業ヲ営ム場合ニ於テハ其ノ兼業ニ属スル資産ヲ併セテ買收スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ買收価額ハ協定ニ依ル
第三十五条 買收代價ハ券面金額ニ依リ五分利付国債証券ヲ以テ之ヲ交付ス此ノ場合ニ於テ五十円未満ノ端数ハ之ヲ券面金額五十円トス
第三十六条 政府ニ於テ地方鉄道ニ接近シ又ハ並行シテ鉄道ヲ敷設シタル為地方鉄道業者カ其ノ接近シ又ハ並行スル区間ノ営業ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ政府ハ其ノ営業廃止ニ因リテ生スル損失ヲ補償スルコトヲ得残存線路ノミニ付営業ヲ継続スル コト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ
補償金額ハ第三十一条乃至第三十三条ノ規定ニ依リテ算出シタル価額ヨリ残存物件ノ価額ヲ控除シタル金額以内ニ於テ政府之ヲ定ム
第三十七条 地方鉄道業者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ免許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト
二 政府ニ於テ又ハ他ノ地方鉄道業者ヲシテ地方鉄道業者ノ計算ニ於テ必要ナル施設若ハ営業ノ管理ヲ為シ又ハ為サシムルコト
三 免許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト
前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス
第三十八条 免許ヲ受ケスシテ地方鉄道ヲ敷設シ又ハ認可ヲ受ケスシテ運輸ヲ開始シタル者ハ百円以上二千円以下ノ罰金ニ処ス
第三十九条 左ノ場合ニ於テハ地方鉄道業者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ十円以上千円以下ノ過料ニ処ス
一 前条ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ為シタルトキ
二 法令ニ基キテ為シタル命令又ハ免許、許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ基キテ為シタル命令ニ違反シタルトキ
三 監査員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタルトキ
四 法令又ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ依リテ為スヘキ屆出、報告其ノ他ノ書類、図面ノ提出若ハ調製ヲ怠リ又ハ虚偽ノ屆出、報告若ハ記載ヲ為シタルトキ
非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
第四十条 前二条ノ規定ハ公共団体カ地方鉄道業ヲ営ム場合ニ之ヲ適用セス
附 則
第四十一条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十二条 私設鉄道法及軽便鉄道法ハ之ヲ廃止ス
旧法ニ依リテ為シタル免許若ハ指定、許可又ハ認可ハ本法ニ依リテ為シタル免許、許可又ハ認可ト看做ス但シ其ノ免許若ハ指定、許可又ハ認可ニ附シタル条件ニシテ本法ニ抵触スルモノハ其ノ效力ヲ失フ
第二条及第三条ノ規定ハ旧法ニ依リテ免許又ハ指定ヲ受ケタルモノニ之ヲ適用セス
第四十三条 軽便鉄道法ニ依リテ軽便鉄道抵当原簿ニ登録セラレタル事項ハ之ヲ鉄道抵当法ニ依リ鉄道抵当原簿ニ登録セラレタルモノト看做シ軽便鉄道抵当原簿ハ鉄道抵当原簿ト看做ス
第四十四条 軽便鉄道法ニ依リテ為シタル処分、手続き其ノ他ノ行為ハ本法中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス