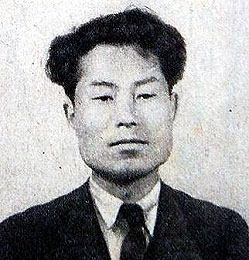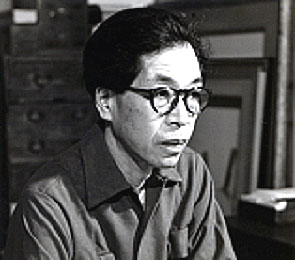
山本丘人(やまもと きゅうじん)は、東京市下谷区上野広小路(現在の台東区上野3丁目)において、東京音楽学校書記だった父・昇と母・ぬい(縫)の一人息子として生まれましたが、本名は正義(まさよし)と言いました。1913年(大正2)に東京府立第三中学校(現在の都立両国高校)に入学しましたが、1915年(大正4)には、東京府立工芸学校金属細工科(現在の都立工芸高等学校)へ転入、彫金を学ぶと共に、広瀬東畝、篠田柏邦に日本画の手ほどきを受けます。
1918年(大正7)に父・昇が亡くなったものの、1919年(大正8)に府立工芸学校卒業後、東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)予備科日本画科に入学、1921年(大正10)には、日本画科選科に編入しました。松岡映丘に師事し、1924年(大正13)に卒業後、映丘主催の画塾「木之華社」に入門します。
1926年(大正15)に新興大和絵会第6回展に出品(以後昭和6年解散時まで毎年出品)、1928年(昭和3)に第9回帝展に「公園の初夏」が初入選し、1929年(昭和4)には、新興大和絵賞・会友に推薦されました。1930年(昭和5)の第11回帝展に「不忍池」が入選し、この作品から雅号「丘人」を使い始め、以後第14回まで連続して入選します。
1934年(昭和9)に映丘門下の杉山寧、浦田正夫、岡田昇、松岡貞夫らと新日本画研究会「瑠爽画社」を結成、1936年(昭和11)に東京府北多摩郡小金井村(現在の小金井市)に転居、文展に「海の微風」を出品し、特選となりました。1940年(昭和15)に「瑠爽画社」が解散、1943年(昭和18)には、川崎小虎を代表として加藤栄三、東山魁夷らと「国土会」を結成します。
1944年(昭和19)に東京美術学校日本画科助教授となり、第4回野間美術奨励賞を受賞しました。太平洋戦争後の1946年(昭和21)に文部省主催第2回日本美術展覧会(日展)審査員として「望流」を出品、1947年(昭和22)には、女子美術専門学校(現在の女子美術大学)教授となります。
1948年(昭和23)に上村松篁ら13名とで「創造美術」を結成、1949年(昭和24)の第2回創造美術展に「草上の秋」を出品、翌年に芸術選奨美術文部大臣賞を受賞しました。1951年(昭和26)に創造美術が新制作派協会(洋画、彫刻、建築)と合同し、新制作協会日本画部となり、国土会解散、東京芸術大学、女子美術大学を辞職します。
1964年(昭和39)に「異郷落日」に対して日本芸術院賞が贈られ、1977年(昭和52)には、文化勲章を受章、文化功労者として顕彰されました。しかし、1985年(昭和60)に病に倒れ入院し、翌年2月10日に、神奈川県において、急性心不全のため、85歳で亡くなっています。
尚、1989年(平成元)には、静岡県駿東郡小山町に「山本丘人記念館・美術館夢呂土(むろど)」が開設されました。
1918年(大正7)に父・昇が亡くなったものの、1919年(大正8)に府立工芸学校卒業後、東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)予備科日本画科に入学、1921年(大正10)には、日本画科選科に編入しました。松岡映丘に師事し、1924年(大正13)に卒業後、映丘主催の画塾「木之華社」に入門します。
1926年(大正15)に新興大和絵会第6回展に出品(以後昭和6年解散時まで毎年出品)、1928年(昭和3)に第9回帝展に「公園の初夏」が初入選し、1929年(昭和4)には、新興大和絵賞・会友に推薦されました。1930年(昭和5)の第11回帝展に「不忍池」が入選し、この作品から雅号「丘人」を使い始め、以後第14回まで連続して入選します。
1934年(昭和9)に映丘門下の杉山寧、浦田正夫、岡田昇、松岡貞夫らと新日本画研究会「瑠爽画社」を結成、1936年(昭和11)に東京府北多摩郡小金井村(現在の小金井市)に転居、文展に「海の微風」を出品し、特選となりました。1940年(昭和15)に「瑠爽画社」が解散、1943年(昭和18)には、川崎小虎を代表として加藤栄三、東山魁夷らと「国土会」を結成します。
1944年(昭和19)に東京美術学校日本画科助教授となり、第4回野間美術奨励賞を受賞しました。太平洋戦争後の1946年(昭和21)に文部省主催第2回日本美術展覧会(日展)審査員として「望流」を出品、1947年(昭和22)には、女子美術専門学校(現在の女子美術大学)教授となります。
1948年(昭和23)に上村松篁ら13名とで「創造美術」を結成、1949年(昭和24)の第2回創造美術展に「草上の秋」を出品、翌年に芸術選奨美術文部大臣賞を受賞しました。1951年(昭和26)に創造美術が新制作派協会(洋画、彫刻、建築)と合同し、新制作協会日本画部となり、国土会解散、東京芸術大学、女子美術大学を辞職します。
1964年(昭和39)に「異郷落日」に対して日本芸術院賞が贈られ、1977年(昭和52)には、文化勲章を受章、文化功労者として顕彰されました。しかし、1985年(昭和60)に病に倒れ入院し、翌年2月10日に、神奈川県において、急性心不全のため、85歳で亡くなっています。
尚、1989年(平成元)には、静岡県駿東郡小山町に「山本丘人記念館・美術館夢呂土(むろど)」が開設されました。
〇山本丘人主要な作品
・「海の微風」(1936年)文展特選
・「到春」(1942年)
・「草上の秋」(1949年)芸術選奨文部大臣賞受賞
・「冬岳」(1953年)
・「北濤」(1955年)東京国立近代美術館蔵
・「夕焼山水(ゆうやけさんすい)」(1961年)平木浮世絵財団蔵
・「異郷落日」(1964年)日本芸術院賞受賞
・「狭霧野(さぎりの)」(1970年)
☆山本丘人関係略年表
・1900年(明治33)4月15日 東京市下谷区上野広小路(現在の台東区上野3丁目)において、東京音楽学校書記だった父・昇と母・ぬい(縫)の一人息子として生まれる
・1902年(明治35) 下谷区上野桜木町34番地に転居する
・1907年(明治40) 東京市下谷区根岸尋常小学校に入学する
・1913年(大正2) 東京市下谷区根岸尋常小学校を卒業。東京府立第三中学校(現在の都立両国高校)に入学する
・1915年(大正4) 東京府立工芸学校金属細工科(現在の都立工芸高等学校)へ転入、彫金を学ぶとともに、在学中に広瀬東畝、篠田柏邦に日本画の手ほどきを受ける
・1918年(大正7) 父昇死去(享年数え年53)、第1回国画創作協会第1回展を見学し感銘を受ける
・1919年(大正8) 府立工芸学校を卒業後、東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)予備科日本画科に入学する
・1920年(大正9) 夏休みの課題コンクールに「娘之坐像」を出品。教授の松岡映丘に高く評価され、以後薫陶を受ける
・1921年(大正10) 日本画科選科に編入。この年「婦女坐像(青梅)」を制作する
・1924年(大正13) 東京美術学校を「白菊」を制作して卒業後、映丘主催の画塾、木之華社に入門する
・1925年(大正14) 第六回帝展に出品するが落選。この頃、本郷洋画研究所に通う
・1926年(大正15) 新興大和絵会第6回展に出品する(以後昭和6年解散時まで毎年出品)
・1927年(昭和2) 新興大和絵会第7回展に直垂姿の松岡映丘(画人の像)を出品する
・1928年(昭和3) 第9回帝展に「公園の初夏」が初入選する
・1929年(昭和4) 新興大和絵賞・会友に推薦される
・1930年(昭和5) 第11回帝展に「不忍池」が入選。この作品から雅号「丘人」を使い始める。以後第14回まで連続して入選する
・1932年(昭和7) 大野美代と結婚、資生堂ギャラリーにて個展開催する
・1934年(昭和9) 映丘門下の杉山寧、浦田正夫、岡田昇、松岡貞夫らと新日本画研究会「瑠爽画社」を結成、夏に伊豆へ取材旅行をする
・1936年(昭和11) 東京府北多摩郡小金井村貫井243(現・小金井市貫井南町4)に転居、文部省美術展覧会鑑査展(文展)に「海の微風」を出品し、特選となる
・1938年(昭和13) 師、松岡映丘が亡くなる(享年58歳)
・1939年(昭和14) 文展、院展作家12名による「綵尚会」(関尚美堂主催)会員となる
・1940年(昭和15) 「瑠爽画社」が解散、高島屋主催「青丘会」会員となり、岡田昇らが「一采社」を結成、顧問格となる
・1942年(昭和17) 第5回新文展に無鑑査出品する
・1943年(昭和18) 川崎小虎を代表として加藤栄三、東山魁夷らと「国土会」を結成する
・1944年(昭和19) 安田靫彦に呼ばれ、東京美術学校日本画科助教授となり、第4回野間美術奨励賞を受賞する
・1946年(昭和21) 文部省主催第2回日本美術展覧会(日展)審査員として「望流」を出品する
・1947年(昭和22) 向井万吉、広田多津、吉岡堅二、福田豊四郎らと下諏訪へ旅行、女子美術専門学校(現・女子美術大学)教授となる
・1948年(昭和23) 上村松篁、秋野不矩、吉岡堅二、福田豊四郎、加藤栄三、澤宏靭、橋本明治、高橋周桑、菊池隆志、向井久万、奥村厚一、広田多津ら13名で「創造美術」を結成する
・1949年(昭和24) 創造美術研究会を開催、第2回創造美術展に「草上の秋」を出品する
・1950年(昭和25) 「草上の秋」に対して芸術選奨美術文部大臣賞が贈られ、岡鹿之助との交友が始まる
・1951年(昭和26) 橋本明治、加藤栄三、東山魁夷、森田沙夷、杉山寧と「未更会」発足、創造美術が新制作派協会(洋画、彫刻、建築)と合同し、新制作協会日本画部となり、国土会解散、東京芸術大学、女子美術大学を辞職する
・1952年(昭和27) ヴェネツィア・ビエンナーレに「山麓」を出品する
・1954年(昭和29) 小倉遊亀、吉岡堅二らと高島屋主催「鼎会」を発足させる
・1956年(昭和31) 奥村土牛、岡鹿之助、中川一政らと兼素洞主催「雨晴会」発足させる
・1957年(昭和32) ブリジストン美術館で個展を開催する
・1959年(昭和34) 貨物船にて渡欧、4月~6月パリ到着滞在後イタリアを巡り、パリでは岡鹿之助と行動を共にする
・1960年(昭和35) 神奈川県中郡大磯町瀧之沢に転居、第25回新制作展に「夕焼け山水」出品する
・1963年(昭和38) 東山魁夷、杉山寧、高山辰雄、西山英雄らと孔雀画廊主催「五山会」を発足させる
・1964年(昭和39) 「異郷落日」に対して日本芸術院賞が贈られる
・1968年(昭和43) サカモト画廊主催「十一月会」が発足する
・1972年(昭和47) 東急百貨店(東京・渋谷)にて「山本丘人展」が開催される
・1974年(昭和49) 新制作協会日本画部全会員が退会し、新たに「創画会」が発足、日展、院展、創画会の会員により「遊星会」が発足する
・1977年(昭和52) 文化勲章を授章、文化功労者として顕彰され、上村松篁、杉山寧、高山辰雄、東山魁夷らと兼素洞主催「白虹会」を発足する
・1983年(昭和58) 軽い脳溢血を起こし静養、遊星展が終了する
・1985年(昭和60) 美代夫人が亡くなり、病に倒れ入院する
・1986年(昭和61)2月10日 神奈川県において、急性心不全のため、85歳で亡くなる
・1989年(平成元) 静岡県駿東郡小山町に「山本丘人記念館・美術館夢呂土(むろど)」が開設される
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
| 571年(欽明天皇32) | 第29代の天皇とされる欽明天皇の命日(新暦5月24日) | 詳細 |
| 905年(延喜5) | 醍醐天皇の命により紀貫之らが『古今和歌集』を撰進する(新暦5月21日) | 詳細 |
| 1155年(久寿2) | 天台宗の僧・歌人慈円の誕生日(新暦5月17日) | 詳細 |
| 1710年(宝永7) | 江戸幕府が漢文体から和文に改訂した「武家諸法度」(宝永令)17ヶ条を発布する(新暦5月13日) | 詳細 |
| 1716年(享保元) | 江戸幕府が五街道の呼称を布達する(新暦6月4日) | 詳細 |
| 1994年(平成6) | 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(WTO設立協定)が調印(翌年1月1日発効)される | 詳細 |